 各部門のご紹介
各部門のご紹介
 アイソトープ部門
アイソトープ部門
アイソトープ部門は、法令に基づく放射性同位元素使用施設として、放射性同位元素の利用を通じた教育・研究促進と放射線防護のために必要不可欠な安全管理等を実施するとともに、施設内のRI非管理区域における分析機器の供用、分析計測サービスを実施しています。
 機器分析部門
機器分析部門
機器分析部門は、個々の研究者や研究室が購入困難な大型化・高性能化した先端機器を集中管理し、高性能な状態を保って多くの研究者が共同利用できるように務めています。現在、高性能の各種分析電子顕微鏡、高分解能多機能X線回折装置、レーザーラマン分光光度計、デジタル核磁気共鳴装置などが設置され、学内の教育研究だけでなく、学外の研究者へと門戸を広げています。
 極低温部門
極低温部門
極低温部門は高圧ガス保安法に則り、液体窒素(沸点-196℃)の管理・供給、液体ヘリウム(沸点-269℃)の製造・管理・供給を行っています。これらの寒剤は容易に極低温環境を実現するため、本学のあらゆる自然科学系分野の研究に様々な形で利用されています。 学内利用者への安定的な供給を維持すると共に、利用者の保安教育にも力を入れています。またこれらの活動に加え、利用者への低温技術のサポート等を実施しています。
 加速器部門
加速器部門
本部門は、加速器の共同利用を通した教育研究支援に関する業務を行うため、平成27年度から研究基盤センターに設置されました。
1.7MVタンデム静電加速器(Pelletron 5SDH2)は、陽子、He、そして希ガスを除くほとんど全ての安定同位体イオンを10MeV程度まで加速することができ、広範な物性研究に利用できます。元素分析として、ラザフォード後方散乱分光法(RBS)等により、物質表面近傍の元素分布の分析、試料中の含有元素同定の分析が可能です。また物質表面改質、 機能性材料創製のための局所的エネルギー付与ができます。これらを通じて、原子・物性物理学、ビーム科学、材料工学、原子力工学、地球科学、考古学、生物学、環境科学など、 極めて広範な分野で有力な装置になっています。今後は、役割を学内だけでなく、広く学外へと広げ、全国の加速器関係施設の中核となるよう努めてまいります。
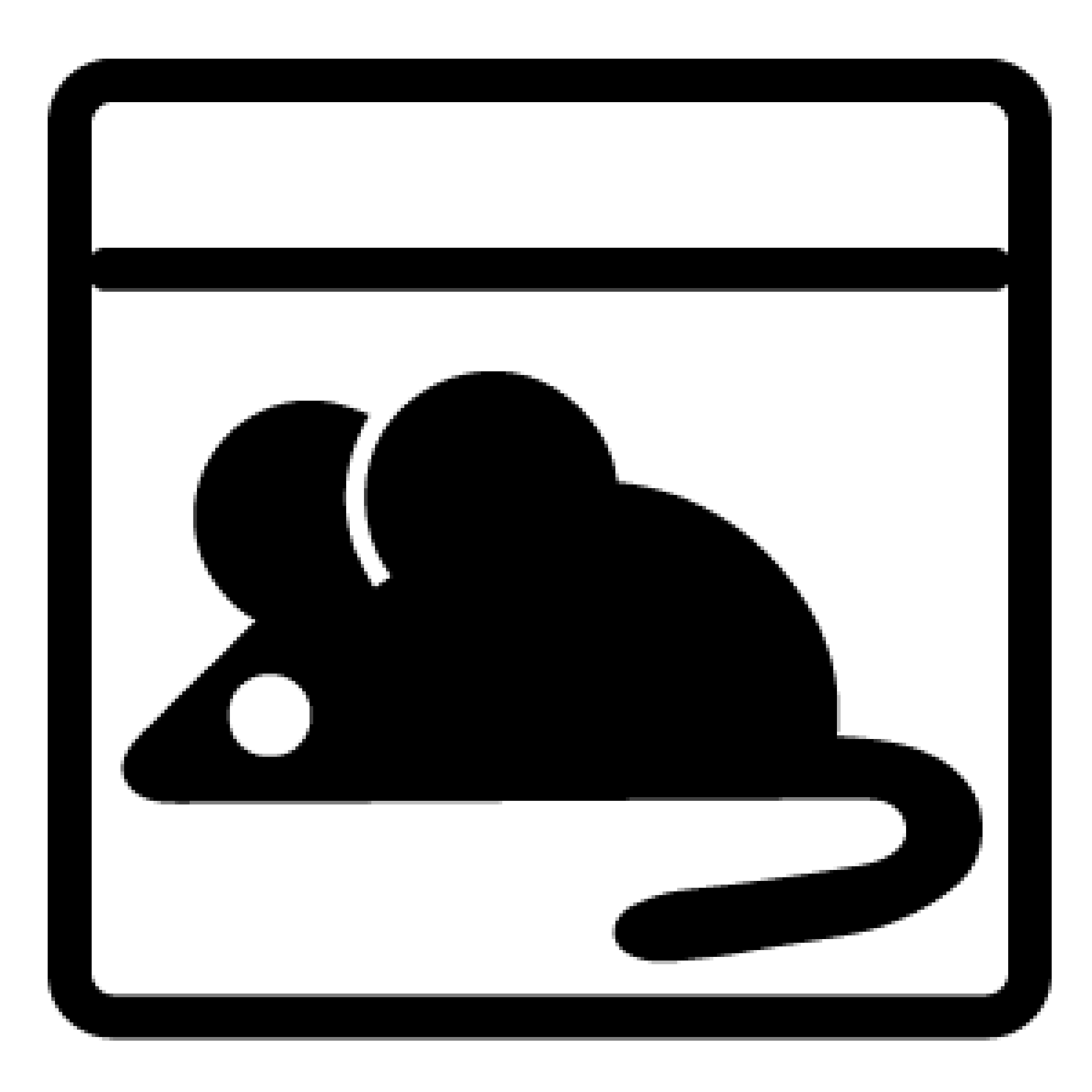 動物機能解析部門 (神戸大学ライフサイエンスラボラトリー)
動物機能解析部門 (神戸大学ライフサイエンスラボラトリー)
動物実験における教育・研究の更なる推進、実験動物の飼育環境の整備、動物実験における安全管理の強化、動物実験に係るコンプライアンスの確立、を目的に「完全個別換気ケージシステム」を取り入れた最新鋭の医科学・生命科学の趨勢に対処するために集約化された統合動物実験教育研究施設で、部局・専攻横断型の拠点形成、高度な研究をサポートする実験動物技術者の養成を目指します。
 放射線統括安全管理室
放射線統括安全管理室
放射線統括安全管理室は、神戸大学の放射線施設、放射性物質、放射線装置の安全管理および教職員等の放射線安全管理全般を統括する目的で設置されました。各施設、部局等と調整しながら学内の放射線安全管理を進めていきます。
 研究設備サポート推進室
研究設備サポート推進室
研究設備サポート推進室は、学内の研究設備をより多くの方が利用できるよう、共同利用の推進に取り組んでいます。 主に、研究設備データベースの管理、センター機器利用サービスのシステム化、センターホームページの運用保守、センター所属職員の人材育成、若手研究者対象の研究会の開催運営等を行っています。 学外との研究設備共同利用においては、「ひょうご神戸研究基盤共同利用機構」の事務局を維持すると共に「大学連携研究設備ネットワーク」とも連携することにより、 学外の教育研究機関との間で有効な共同利用の推進に努めています。
